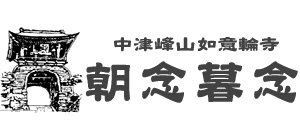
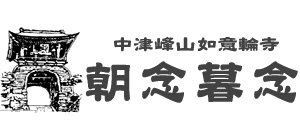
第218号
|
|
|
|
|
|
|
|
釈尊はウルビーラの森で仲間達と修行されいた。それは生きる限界に挑戦したというべき苦行であった。だが、悟りを得られない。それを捨てた釈尊は尼連禅河で沐浴された。そのとき、生きているのか死んでいるのか分からないほど体力を消耗されていた。そこへ村娘スジャータが乳粥を供養した。日一日と回復され再び修行を始められた。 六年間の修行の後、菩提樹下で悟りを得た。菩提樹下で一週間心地よい覚りを味わった後、禅定を離れニグローダ樹の下に行き、解脱の味わいを楽しまれた。七日過ぎてこの樹のもとを去ってムチャリンダ樹下で解脱の楽を味わわれた。そのとき、時ならぬ雲があらわれて、七日間雨が続き、冷風が吹いて、闇が四面を覆った。竜王が身をもって釈尊を覆い、雨を防ぎ、暖をとって釈尊を守った。七日後空は晴れた。また七日後禅定より立ち、その樹のもとを離れてラージャタナ樹の下で解脱の楽しみを味わわれた。 そこにウッカラ村からタブサとパルリカという商人が通りかかった。天界の親戚から「世尊は今初めて悟りをひらき、ラージャタナ樹の下におわすので、麦粉と蜜をささげるとよい」という勧めを聞き、釈尊の御前に詣でそのようにして「佛と法とに」帰依することを誓っ 此岸と彼岸の話 た。最初に二宝に帰依した信者となった。また七日過ぎてニグローダ樹の下に坐された。 釈尊は概ねこのようなことを思われた「私の覚りは深遠なもので人々に説いてもとうていわかるまい。それを人に伝えるのはただ々々疲れを増すに過ぎぬであろう」と。かくして法を説こうとはされなかった。そのとき、梵天が釈尊の御心を知って「世尊、なにとぞ法をお説き下さい。世には垢に染まぬ智慧の眼を持つものもおります。もし彼等が法を聞かないなら滅びてしまいます。彼等は必ず世尊の法を証るでありましょう」とお願いした。 釈尊は梵天の勧請により、人々に対する憐みの心から、その佛の眼をもって世界を眺められた。そして、法を説く決心をされた。 覚りの地ブダガヤからベナレス郊外の鹿野苑を目指されて歩いておられた。前にはガンジスの大河が横たわっている。渡し守に「私を渡してくれぬか」と。渡し守は「渡し賃のないものは渡せぬ」といった。それを聞くと同時に釈尊は向こう岸に飛んでしまった。 この話は二つの意味をもつ、一つはこれ以降「出家から渡し賃を取ることはまかりならぬ」と当時この地方の主、マガダ国のビンビサーラ王がおふれをだしたという歴史的事実。第二は 「此の岸」から「彼の岸」へ飛んで行ったという象徴的なものである。「此の岸」は我々の住む世界、我々の世界はだましだまされ、怨み怨みの煩悩渦巻くこの世。「彼の岸」は覚りの世界。すでに釈尊は「彼岸」に居られたのである。 鹿野苑に近づくとかってのウルビーラ森仲間五人がいた。彼等は「向こうから来るのはゴータマだぞ、彼は苦行をあきらめたくせに、最近覚ったと言う奴だ。相手にしないでおこう」と申し合わせた。ところが釈尊が近づくにつれて、五人の仲間は「ゴータマよ、私達におまえの覚とやらを教えておくれ」とたのんだ。「ゴータマと呼ぶなかれ、私はブッダであるぞ」五人の仲間は「どうか、お教えいただき、弟子にしてください」とひれ伏してお願いをした。こうして五人の比丘に初めて説法をした。初めて法の輪を転がしたとし「初転法輪」という。結果、法をまもる集団僧伽(サンガ)ができた。佛教の誕生である。 因みに仏陀・釈尊が一週間づつ七回覚りを楽しまれることのなかから七・七日の供養への萌芽が見られる。
ホテルに帰って、一息つくまでもなく、パーティの準備だ。お土産だげでも数々ある。ところが皆んなに秘密だが、私は今日の山越えのバス旅で右に左に振すったお腹のぐわいが良くない。 細川団長、添乗員の大嶋 さん等とあわただし準備が続く、早くもお客様ダショ・サンガイ・ワングチィック氏が見える。英語の肩書きではわからなかったが、自ら文化庁長官と日本語でいう。訪日経験があり、姫路まで来たという「その南、海に架かった橋を渡ると四国だ」といってもわかろうはずはあるまい。政府高官といえども全員「ゴ」を着ている。目のあたりにして文化庁長官から直接「ゴ」の解説を聞く。身丈がくるぶしまである着物を七分に膝までたくし上げて着る。それを後ろに大きくひだをとって帯でとめる。だからゆっくり帯の上でたるみができる。要するにほところが深いのである。長官はここが広いので賄賂でも何でもいくらでもはいると冗談をいう。「ゴ」の下には「テゴ」とよぶ襦袢を着ている。「テゴ」は「ゴ」より十㎝余り長い。それを折り返すとカフスになる。今はラゲイという筒状の袖口をつけて白いカフスとしている。足元は先述のハイソックスである。このスタイルは坊さん方がプナカに避寒するまで続く、その後はジーンズをはくなどが首都テェンプーの若者の粋なスタイルであるという。 文化庁長官に続いて王室警護室長、御典医、文部次官、王室秘書室長、軍隊警務局長、ETCの政府の要人、ドウルック航空の社長が婦人を伴って続き、通産大臣が自分で車(トヨタ四駆、ナンバーがBGだから公用車か)を運転して来る。その間に日本に留学した七人 が夫人同伴で集まった。彼等は次世代、国家を代表する面々である。皆んながそろったところに昨日の大僧正と次席僧正を我々を世話してくれている観光会社マンダラツアーの社長夫人が車でお迎えしてきた。当方の十九人に合わせ四十人の大パーティになった。 最初に名誉団長の私と細川団長がパーティ参加のお礼、留学生を通じた日本とくに徳島との交流等の挨拶、タシ君が通訳である。先方、大僧正と大臣が挨拶。当地から持参したお土産、金一封を贈った。ところが金一封を受け取った通産大臣はそのまま大僧正に渡してしまった。 ウエルカムドリンクより大僧正の横に座った私は気になることがあった。僧坊の戒律は午後の食事を禁じる。我々も行の時それを守る。昨日の表敬訪問のとき、チャイとクッキーを大僧正はチャイのみしか口にしなかった。今日はどうだろうか。ジュースを飲んでいる。私もそれに習う。料理になってもスープぐらいしか手をださない。幸いか、先ほどからお腹の調子が悪いのでちょうど良い。とはいえ目の前の国家の要人相手に作った料理には魅力がある。通産省大臣の傘下の元留学生が通訳してくれ大僧正と懇談「君と仲良くなるご祈祷をするが良いか」「是非願いたいこれから猊下と何度でもお会いできるよう願っている」「今日金一封を頂いたが、どういう金か」「我々の気持ちだけだから気 にしないで頂きたい」「これからこういうことをしないでつきあっていこう」等々。最高位のジェイケンポ猊下から高野山管長猊下への返書を頂いた このとき「今度来たときはジェイケンポ猊下と会わせる」「各ゾンは俺が管理しているのだからどこでも入れ」等々。日本に留学経験のある七人が通訳を兼ね、中心になって和やかに歓談する。日本の想いで、仕事のこと、料理のことなどなど楽しいひとときである。 ブータン料理はキノコ、そば(日本料理とは違う)、チキン、牛肉、という食材だが、みんな激辛である。インド料理はカレー中心だが、こちらは唐辛子中心に味を付けた煮込み風。その地方の料理が現地で食べるのが一番、ことに現地の人が食べる味がもっともおいしい。坊さん方も気をつかってか少々食べていた私も一通りは味わった。 坊さん方も居心地が良かったのか。二時間あまり臨席してくれた。あとの人たちは坊さんが帰らなければ席を立たないのがマナーらしい。坊さんが退座されたあと順次偉い順に帰る。鬼がいなくなれば気楽にやるのはいずれの国も同じらしい。夜も更けるまで楽しく歓談した。
今回の移植の感想を羅列してみたい。ただ、十分な検討ができていないので、独 断と偏見をお許し願いたい。 二月二十四日午後七時のNHKテレビニュースの途中でドナーカードをもった脳死状態の方がでたという緊急ニュースがいった。時間を経るにしたがってドナーカードの所持者の身元が分かるような報道になった。一方、臓器移植法にしたがって脳死判定が行われた。が、その日は脳波があって脳死ではないとされた。 先ず、医学上は十分検討され、シュミレーション、実際の演習まで行われていた。だが、マスコミの方はなにもなされていなかった。「脳死を、さらに移植医療をどう考えるのか」をデスク、取材記者一人々々の教養、資質が問われたのである。最初の脳死判定で「生」とされたことはそれを考えさせられる時間となった。私はこの時間を佛様の御心と思う。もし、そのまま進んでいたら、ドナーの家、家族、退去風景、はては葬儀まで中継したのではなかろうか。また、私は「死は点でなく線である」というのが持論である。ある瞬間から死に至るのではない。息を引き取ったら、枕返し、お通夜、末期の水、葬儀、骨上げ、初七日から四十九日という一連のことで死は実感されていくのである。それを脳死という点で処理されるところだった。それが家族も納得への時間となったことだろう。 次に家族は実際に臓器を摘出した段階でこれほど体 内が空になると思っただろうか。摘出後の遺体をどういう気持ちの整理をつけて葬儀を執り行ったのだろうか。私の母は東京オリンピックの年胃癌で亡くなった。当時は癌告知はなかった。疑問をもった母は自分で先生方に死後の病理解剖を依頼した。結果、お腹のほとんどに癌の転移が見られ、病巣を摘出すると体内は空だった。しかし、毎日々々体はやせ衰え。反対にお腹をに突き破るほど毎日増殖した癌の存在。食事は全部詰まったままの母を知ってる私はこの手術(解剖)で母はスッキリしたと信じた。さてさて今回は家族がどう自分を納得させただろうか。 次に私が脳死と出会った経験は三回、初回は雲膜下出血のX氏。ある理由で医者から「脳は死んでいる」と告げられた。「脳死」という日本語がない時代だった。その後、一週間で亡くなった。日本語で「息を引き取った」という言葉との矛盾でしばらく頭が混乱した。二回目、三回目は交通事故、その時に見舞いに行くとなぜかICUに入れてくれ患者の側まで行った。長男にはもう脳死状態と告げられいて、諸々の悩みを話す。つい患者の横で長居となった。患者がどうしても目に映る。事故から一週間。髭も伸び、顔色はすこぶる良い。息子の看護で安心して寝ている。それが実感だった。 次に「人は死んでも、その人の臓器どこかで生きてる」 とのマスコミ報道があった。生きているならなぜ脳死なのか。死んだからこそ摘出可能ではないのか。ここでドナーの家族は死を明確にしなければならぬ。普通なら焼けてしまう部分を少々利用しているに過ぎない。火葬で骨を拾った後、骨壺に入らぬ遺骨を、執着なしにそのままにして帰る。それと同様に考えることがドナー家族には絶対必要だ。受けた側の立場になってみると、新製品の人工心臓が使われただけのことである。それは誰々の生命というものではない。これが家族の同意とならない限り「ドナーカード」を書くべきではないと私は思う。 「ドナーカード」は実行を確実なものにしたカードでないと今も待ち続けるレシピエントに礼を失する。先のことを含め家族の心が同じでなければならぬ。待つ身はカードをもつ人が一人でも多く実行されることを願っている。失礼を顧みずいうとそれは「餓鬼」である。それは人の死をもって己が生きようとするからだ。だが、その「餓鬼ぶり」が生きる意欲をかき立てている。生きる糧なのだ。「ドナーカード」を持つ人と家族は「施餓鬼」の極を実行される人といえる。まさに「菩薩行」だ。 そこで私は「ドナーカード」を書くと同時に死の準備を提案したい。自分の遺骨として残すべき爪、髪、歯等々自分の分身。好きな蒐 集品等々気にいった入れ物に収めておくべきだ。父が献体した後に残したのはこれだった。後、返還された遺骨には違和感を憶えた。 佛教にはジャータカ(お釈迦様の前世の物語)のなかに「飢えた虎が向こうから来るのを見て、何もあたえるものがない釈尊は自分の身体をあたえた」というのがあるのみ。新しい事態に各宗教教団は模索中である。
二月十三日、脇町高校で新任の私に地理の教師として一から教わった恩人の元池田高校長折目忠治先生の勲四等叙勲祝賀会が池田町であった。先生の池田高校長六年間は甲子園出場八回、うち優勝六回という池高野球全盛時代だった。一時は校長室に高校野球の全優勝旗が集まったという。高校長多しといえどもこんな運に恵まれる校長は少ない。運も実力の内、まさに先生は水を得た魚のごとく運を自分のものにされた。とはいっても日本の池田高校となったからご苦労もたいへんであったらしい。その第一歩が始まった想い出の政海旅館でとのことだった。このような先生故に人が慕ったのだろう。先生の挨拶に私の名前を出てきたのは汗顔の極み。会の最後に皆んなで声たからかに「東雲の・・・」と池高校歌唄ったのは圧巻であった。甲子園効果を実感した次第。